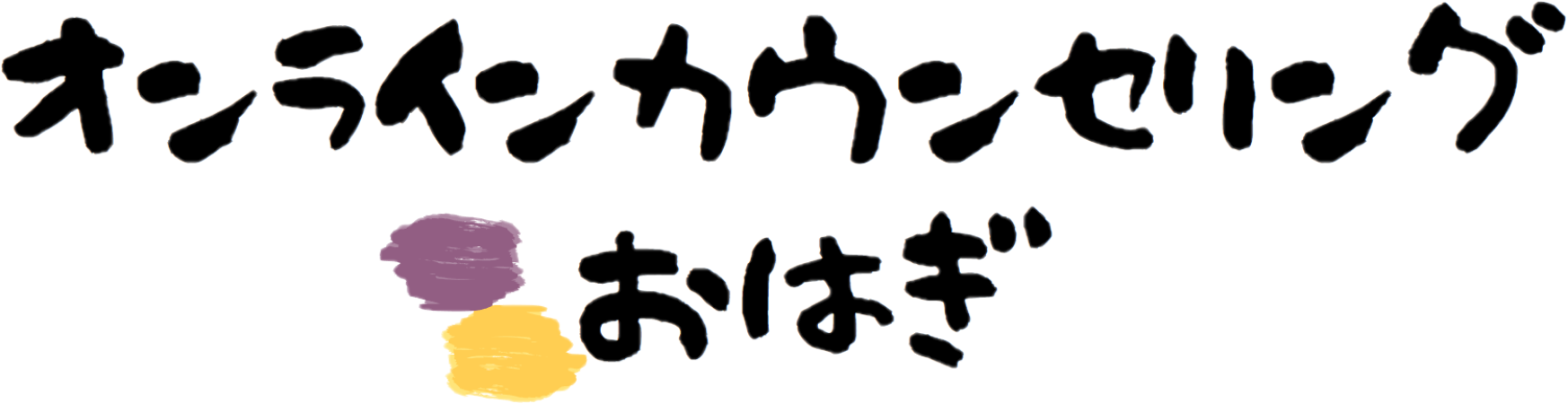アドラー(Alfred Adler)
アドラー(Alfred Adler)
"アドラー(Adler, A.)"は、1870年から1937年にオーストリアで活躍した精神科医です。
『個人心理学』の創始者として知られています。
アドラーはオーストリアのウィーン郊外で、7人兄弟の次男として生まれます。
幼い頃にくる病(筋肉や骨の痛みなどが生じる病気)と呼ばれる病気を経験します。
ウィーン大学医学部を卒業後、ウィーンで活躍し、『精神分析』を創始した”フロイト(Freud, S.)”のサークルに招待されます。
しかし、アドラーはフロイトから学びつつも次第に意見の違いを感じるようになります。
それは、人の心や『精神障害』をどのように理解し、治療していくかということについて、フロイトは生物学的な視点や個人の精神内界を重視したのに対し、アドラーは社会学的な視点や対人関係に焦点を当てていた点が挙げられます。
このような根本的な違いから、アドラーはフロイトのサークルを抜け、決別していくことになります。
その後アドラーの考えや理論は個人心理学と呼ばれるようになり、『人間性心理学』などの発展に大きな影響を与えることになります。
アドラーの考えははじめ劣等感を巡って展開されていきました。
これは、アドラーが幼い頃に身体的な病気で苦しんだことに由来していると考えられています。
これは『器官劣等性』の研究としてまとめられ、幼児期に生じた身体的障害がその後のパーナリティ(人格)の発達にどのような影響を及ぼすかについて考察しています。
その中で、『劣等感コンプレックス』などの概念が生み出されていきます。
そして、器官劣等性の考えはその後、哲学者である”ニーチェ(Nietzsche, F. W.)”の影響を受け、劣等感の『補償』(劣等感を克服して自らの弱点を補おうとする心の働き)といった概念へと発展します。
それにより、アドラーは人の人生の根本的動因には『権力(カ)への意志(will to power)』があると考えるようになります。
このように、個人心理学では人の劣等感を克服しようとする心の働きや目標追求性に注目します。
そのため、精神分析の人間観や治療理論は原因論で展開されているのに対し、個人心理学では目的論が重視されるようになります。
また、個人について、これまでは複数の動因の集合体と捉えていたのに対し、次第に個人を分割できない統一体として理解するようになります。
さらに、社会についても、これまで個人から社会を理解しようとしていたのに対し、社会を中心に個人をみるようになます。
そして人間集団を分割できない統一体として捉え、個人をその中に不可分に組み込ま れた有機的部分として理解しようとます。
このような考えに基づき『共同体感覚』などの考えが生み出されていきます。
参考・引用文献
森岡正芳編 (2022) 『臨床心理学中事典』野島一彦 (監修), 遠見書房.
\この記事を書いた人/
臨床心理士・公認心理師
上岡 晶
Ueoka Sho
精神科・心療内科での勤務を経て、2023年から「オンラインカウンセリングおはぎ」を開業しました。私のカウンセリングを受けてくださる方が少しでも望まれる生活を送れるように、一緒に歩んでいきたいと考えています。