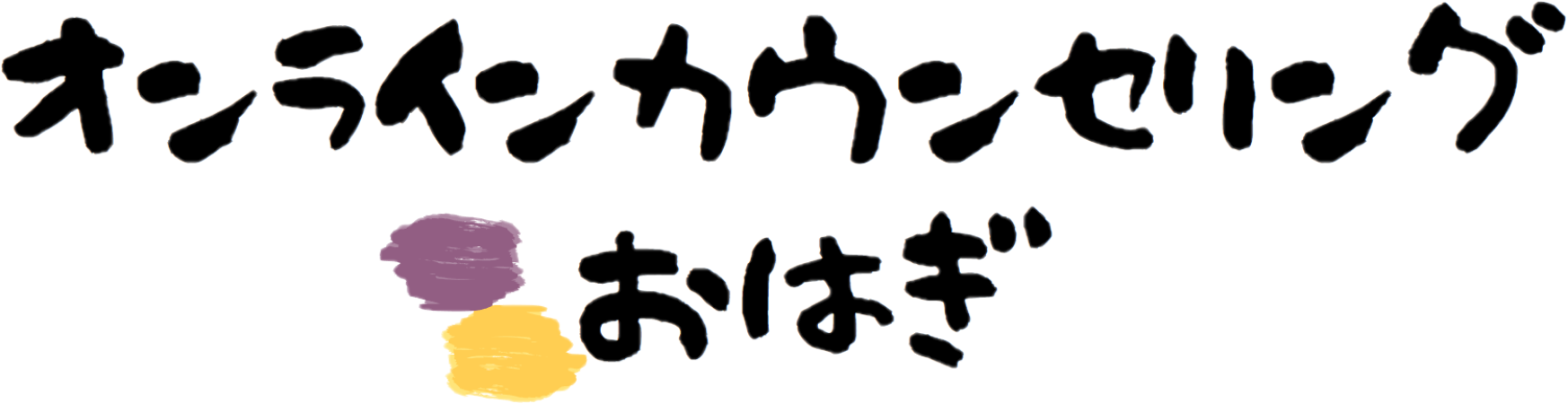防衛機制(defense mechanisms)
防衛機制
『防衛機制』は、『精神分析』を創始した”フロイト(Freud, S.)”により提唱された理論になります。
そして、その後”アンナ・フロイト(Freud, A.)”により整理され『自我心理学』の中に組み込まれていきました。
また、“クライン(Klein, M.)”は『対象関係論』の立場から防衛機制を応用し、『原始的防衛機制』の概念を生み出していきます。
防衛機制とは、『意識』の領域にあると心的苦痛を引き起こす衝動や感情、体験、欲求などに対して、心の安定を保つためにそれらを『無意識』の領域に追いやろうとする『自我』の保護的な働きを指します。
このような、個人の心を守るための自我の様々な防護法を防衛機制と呼びます。
また、使用される防衛機制は個人の傾向や状況により異なりますが、個人が性格として同一の防衛機制を常に基本的に用いる場合もあります。
そのことを”ライヒ(Reich, W)”は『性格の鎧(よろい)』、アンナ・フロイトは『永続的防衛』と呼び理解しようとしました。
フロイトが提唱し、アンナ・フロイトが整理した防衛機制には、『退行』、『抑圧』、『反動形成』、『隔離(分離)』、『合理化』、『置き換え』、『打ち消し』、『投影』、『取り入れ』、『同一化(同一視)』、『昇華』、『知性化』などがあります。
また、クラインが対象関係論の立場から提唱した原始的防衛機制には、『分裂』、『投影同一化』、『否認』、『原始的理想化』、『躁的防衛』などがあるとされています。
- 退行(regression)
退行とは、現在の状態より以前の状態へ、あるいは未発達な段階へ逆戻りすることを指します。
退行についてフロイトは病的な心の働きであると捉えていましたが、アンナ・フロイトは自我が自らを守るための心の機能であると捉えました。
また、"クリス(Kris, E.)"は芸術家の分析や研究を通して退行の創造的な働きを明らかにし『自我による自我のための退行』の概念を提唱しました。
さらに、”ウィニコット(Winnicott, D. W.)”は患者が治療中に幼児的な退行状態にいたることは不可欠なことだと考え『治療的退行』という言葉を用いて理解しようとしました。- 抑圧(repression)
抑圧とは、意識の領域にあると心的苦痛や不快を引き起こす衝動や感情、体験、欲求を、意識から隔離し、無意識の領域に追いやろうとする心の働きを指します。
これは意識的に行われる抑制とは異なり、無意識的に起こる心の働きであると考えられています。抑圧は内部の危険を予知することで生じ、『抑圧され無意識に追いやられたものは消えることがなく、『神経症』の症状や、『夢』、『失錯行為』などといった別の形に歪曲され現れることがあると考えられています。
しかし、抑圧により個人は不安や葛藤に振り回されず適応的な生活を送ることが可能になるなど適応的な機能も明らかにされています。
- 反動形成(reaction formation)
反動形成 とは、衝動を意識化すると心理的苦痛が生じるため、それを防ぐためにその衝動とは反対方向の態度を過度に強調しようとする心の働きを指します。
反動形成により、憎悪が愛情に、残忍さが優しさに、頑固さが従順さに、変化する場合適応的な行動に繋がりますが、逆の変化が見られた場合不適応的な行動に繋がる可能性があるとされています。
- 隔離(分離)(isolation)
隔離(分離)とは、意識の領域にあると心理的苦痛を引き起こす衝動や感情などを、意識の領域から切り離そうとする心の働きを指します。
隔離は心を保護するために、思考と感情を切り離したり、相異なった行為や観念などの間に存在する関係を絶つように働くと考えられています。
- 合理化(rationalization)
合理化 とは、自分の望んだ言動を不安を起こすことなく遂行するために、自分の言動について論理的で妥当な一貫性のある説明を行おうとする心の働きを指します。
合理化は、自分の行動を正当化することで、自分の心の傷や葛藤を回避し、真の動機を隠すように働きます。攻撃的な行動に対して合理化が使用される場合、個人は自身の攻撃性を正当化し自身の行動の真の動機を自覚しないため、攻撃的な行動が継続し問題へと発展する可能性もあるとされています。
- 置き換え(displacement)
置き換えとは、ある対象に向けられるはずの感情や関心、焦点づけがその対象を離れ、自我にとってより受け入 れられやすい別の対象に移る心の働きを指します。
ある対象に対して抱いている攻撃的な感情が、別の対象に置き換えられた場合(八つ当たりなど)、対人関係の問題へと発展する可能性もあるとされています。
また、置き換える対象が自分自身に移る場合もあり、その現象は『自己への向き換え』と呼ばれています。
- 打ち消し(undoing)
打ち消しとは、過去の思考や行動に伴う罪悪感や恥ずかしさの感情を、それとは反対の意味をもつ思考や行動によって打ち消そうとする心の働きを指します。
お祓いなどの宗教的な儀式も打ち消しの一つと考えられています。
- 投影(projection)
投影とは、自分の心の中にある感情や欲望を他者がもっているものと認知する現象を指します。
『投射』と呼ばれる場合もあります。意識の領域にあると心理的苦痛を引く起こす衝動や感情などが抑圧され投影がされた場合、他者との不適応的な関係に繋がる可能性があると考えられています。
- 取り入れ(introjection)
取り入れとは、対象(他者)の心の中にある感情や欲望などの諸機能を自分の精神表象として幻想的に取り込もうとする心の働きを指します。
『取り込み』、『摂取』ともよばれています。投影は、自分の心の中にあるものを他者に投影するのに対し、取り入れは他者の心の中にあるものを自分に取り入れる働きになります。
- 同一化(同一視)(identification)
同一化(同一視)とは、心理的苦痛を引き起こす感情(不安や劣等感など)を回避するため、対象(他者)に自分を近づけ重ね合わせようとする心の働きを指します。
これは、他者と自分の区別がされている取り入れとは異なり、他者と自分の区別が希薄になり行われると考えられています。- 昇華(sublimation)
昇華とは、衝動や欲求が本来の目標を放棄し、より社会的な価値や道徳に適合する目標に向け換えられる心の働きを指します。
つまり、昇華により個人の衝動や欲求は攻撃的、性的な満足以外の目的 で、社会的に承認される価値あるものに向け換えられます。
そのため、『成功的防衛』もしくは『適応的防衛』とも呼ばれています。このような昇華の働きにより、人は満たされない無意識的な衝動や欲求を充足するために文化的な活動を行い、それが文化発達の源泉にもなると考えられています。
- 知性化(intellectualization)
知性化とは、衝動や欲求を表出したり行動に移す代わりに、一応これを抑圧し論理的な思考過程や知識の獲得や伝達に置き換える心の機能を指します。
知性化は昇華と同様に現在の社会では社会適応性の高い防衛機制と考えられていますが、知性化が過剰に用いられる場合、合理性の逸脱した思考に陥り不適応的な状態になる可能性があると考えられています。
参考・引用文献
森岡正芳編 (2022) 『臨床心理学中事典』野島一彦 (監修), 遠見書房.
日本心理臨床学会編(2011)『心理臨床学事典』 丸善出版.
横川滋章・橋爪龍太郎(2015)『生い立ちと業績から学ぶ精神分析入門 22人のフロイトの後継者たち 』 乾 吉佑 (監修), 創元社.
\この記事を書いた人/
臨床心理士・公認心理師
上岡 晶
Ueoka Sho
精神科・心療内科での勤務を経て、2023年から「オンラインカウンセリングおはぎ」を開業しました。私のカウンセリングを受けてくださる方が少しでも望まれる生活を送れるように、一緒に歩んでいきたいと考えています。