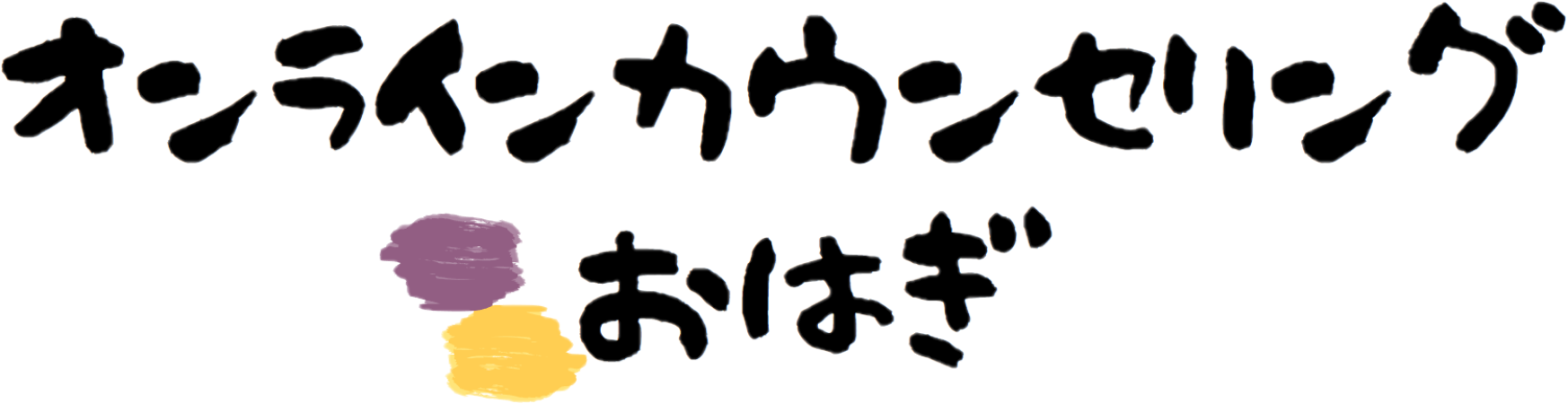自我心理学(ego psychology)
自我心理学
『自我心理学』は、”フロイト(Freud, S.)”が創始した『精神分析』の流れを汲む『心理療法』の1つになります。
”アンナ・フロイト(Freud, A.)”や”ハルトマン(Hartmann, H.)”などが創始者として知られています。
自我心理学は、フロイトが提唱した『心的構造論』を基盤に発展した心理療法であり、『自我』の概念を中心に人の心や『精神障害』を理解し治療していくことを目的としています。
1920年頃より以前の精神分析では、人の心について『心的局所論』(人の心を『意識』、『前意識』、『無意識』の3つの領域に分けて理解する理論)を基盤に理解しようとし、無意識の内容を明らかにすることが精神障害の治療に効果的であると考えていました。
しかし1920年以降は、人の心がどのような機能を持ちそれぞれがどのように作用しあっているのかが問題となり、心的構造論(人の心を『イド(エス)』、自我、『超自我』の3つの役割から理解しようとする理論)が提唱されました。
心的構造論では、自我は社会や現実に適応するために、快感原則に従い活動するイド(エス)や道徳原則に従い活動する超自我の働きを調整し、バランスを維持するように機能すると考えられています。
そしてこのような自我の働きは自我の『防衛機制』と呼ばれ、これが上手く機能しない場合に心の安定が損なわれていき、場合によっては『神経症』の症状に発展し社会や現実での適応が困難になっていくと考えました。
このように、フロイトが想定した心的構造論では、現実適応に向けてイド(エス)や超自我の対立や葛藤の調整を行うといった自我の防衛機能や、治療の『抵抗』を生み出す自我の働きに注目していました。
しかし、1930年代になるとアンナ・フロイトやハルトマン、”エリク・エリクソン(Erikson, E. H.)”らが現れ、自我はイド(エス)や超自我の対立や葛藤とは無関係に形成される自律した機能をもつ存在であると認識されていくようになります。
中でも、アンナ・フロイトは、自我の防衛機制の概念の整理を行い、自我の防衛的な側面だけでなく、適応的な働きを明らかにしていきます。
また、ハルトマンは、自我の自律的、積極的な適応機能について注目し、『自律的自我』や『葛藤外の自我領域』の概念を提唱します。
さらに、エリクソンは、自我の発達は社会との相互作用の中で起こると考え、『ライフサイクル論』や『アイデンティティ』などの概念を提唱しました。
このように自我心理学では、無意識内容を理解することよりも自我の強さや自我の持つ「現実機能」(現実検討力)や「防衛機能」、「適応機能」、「自律機能」、「統合機能」などを理解していくことを重視します。
そして、精神障害や人の心の健康が損なわれている状態を自我の機能が上手く機能せず弱まっている状態と捉え、それらを支持、強化し機能を促進していくことが治療や心の健康に繋がっていくと考えます。
参考・引用文献
森岡正芳編 (2022) 『臨床心理学中事典』野島一彦 (監修), 遠見書房.
日本心理臨床学会編(2011)『心理臨床学事典』 丸善出版.
横川滋章・橋爪龍太郎(2015)『生い立ちと業績から学ぶ精神分析入門 22人のフロイトの後継者たち 』 乾 吉佑 (監修), 創元社.
\動画での解説はこちら/
\この記事を書いた人/
臨床心理士・公認心理師
上岡 晶
Ueoka Sho
精神科・心療内科での勤務を経て、2023年から「オンラインカウンセリングおはぎ」を開業しました。私のカウンセリングを受けてくださる方が少しでも望まれる生活を送れるように、一緒に歩んでいきたいと考えています。