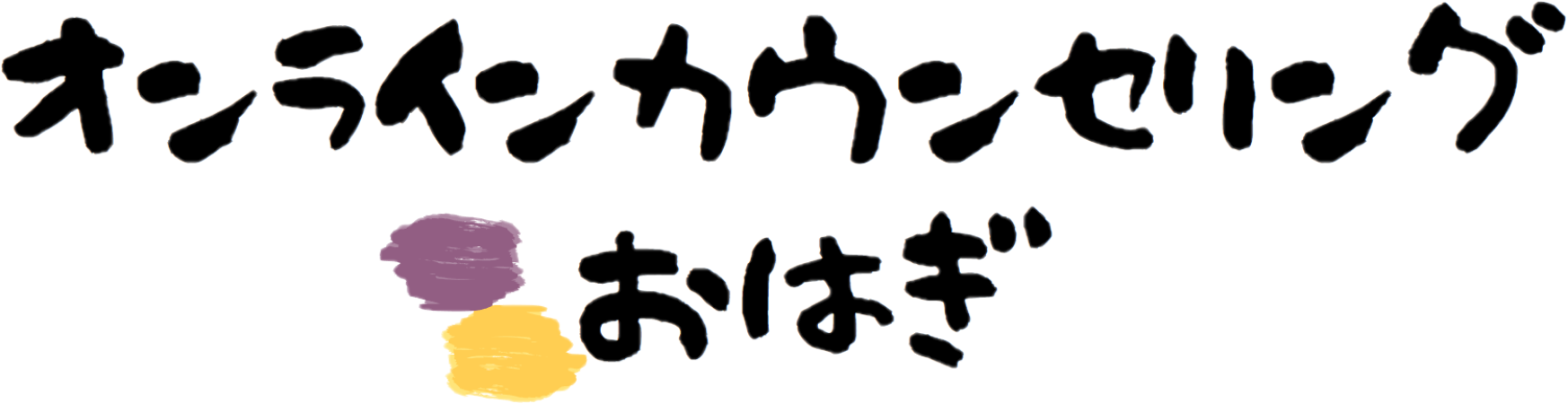個人心理学(individual psychology)
個人心理学
『個人心理学』は、1900年代に"アドラー(Adler, A.)"が創始し、後継者たちによって継承され発展した心理療法です。
個人心理学では、人間や集団を分割できないものとして捉えることを特徴とします。
個人は英語でindividualと表記しますが、この語源はラテン語のindividuumであり「分割できない」といった意味を持ちます。
しかし、個人心理学という名前が個人のみに焦点を当てるといった印象を与えやすいため、日本では『アドラー心理学』の名称が多く使用されています。
アドラーの考えははじめ劣等感を巡って展開されていきました。
これは、アドラーが幼い頃に身体的な病気で苦しんだことに由来していると考えられています。
これは『器官劣等性』の研究としてまとめられ、幼児期に生じた身体的障害がその後のパーナリティ(人格)の発達にどのような影響を及ぼすかについて考察しています。
その中で、『劣等感コンプレックス』などの概念が生み出されていきます。
そして、器官劣等性の考えはその後、哲学者である”ニーチェ(Nietzsche, F. W.)”の影響を受け、劣等感の『補償』(劣等感を克服して自らの弱点を補おうとする心の働き)といった概念へと発展します。
それにより、アドラーは人の人生の根本的動因には『権力(カ)への意志(will to power)』があると考えるようになります。
個人心理学の人間観や治療理論は以下のような特徴を持ちます。
「目的論(teleology)」
全ての人間行動には目的があると考える立場を指します。
アドラーは常に人間の主体的な決断力を信じていました。
そのため、個人の目的やそれに向けて個人がどのように関わっているのかに焦点が当てられ、精神内界の諸問題に行動の原因を帰することを重視しません。
このような目的論により、個人心理学では「すべての人はあらゆることをすることができる」といった『治療的楽観主義』を持つことができます。
「全体論(holism)」
物事を対立的に捉えるのではなく、それ以上分割できない全体と考える立場を指します。
例えば、身体と精神、『意識』と『無意識』などは一見対立しているように見えますが、実は一つの目標を追求し達成 するために分業しているにすぎないと捉えます。
全体論の考えは、『心身相関』の考えに基づく『心身医学』の発展に影響を与えました。
また、意識と無意識の対立を想定しないといった発想は、"マズロー(Maslow, A. H.)”などに大きな影響を与え、その後の『人間性心理学』の発展に繋がっていきます。
「対人関係論(interpersonal theory)」
精神内界でなく、個人と環境との相互作用を分析対象にするという立場を指します。
個人心理学では、行動の目的は内的なものでなく、環境とのかかわりの様式の中にあると考えます。
そして人の究極的な目的は人間共同体への所属(『共同体感覚』)であり、その下位に個人の人生目標があると考えます。
「現象学(phenomenology)」
人間行動を決定するのは客観的な世界そのものではなく、客観的な世界を主観的にどう認知するかであると考える立場を指します。
個人心理学では、人は自分にとって意味のあるものだけを、しかも自分の信念に合致するように歪曲して認知すると考えます。
そして、記憶を想起する際にも同様のことが起こりうるため、過去の事象についての情報収集は、現在の原因追求の手段としては用いることができないと考えます。
これがアドラーの無意識に対する考え方になります。
以上のような人間観や治療理論からアドラーは『精神障害』について、全ての『精神障害』は自己世界認知の誤りに起因し、症状はその副産物ではないかと考えました。
「目的論」の立場から、症状を対人関係上の目標を達成するために使用され る無意識的な道具であると捉え、また「対人関係論」の立場からは、症状をコミニケーション行動として捉えます。
そして症状を自己の挫折を覆い隠す口実として作り出され使用されるものであると考えました。
そのため、症状を理解するためには、個人の内面だけに焦点を当てるのはではなく、対人関係システムの中で理解されなければいけないと考え、究極的な治療目標は共同体への所属や共同体感覚の育成であると考えました。
個人心理学では、治療目標を共同体感覚の育成に置いているため、個人のカウンセリングだけでなく、複数のクライエントを同時に面接する集団カウンセリングや、1対1の相談を聴衆に公開して行う公開カウンセリングのような形も取られました。
これらは、後の『集団精神療法』や『家族療法』の先駆けとなり、その発展に大きな影響を与えることとなりました。
- 劣等感コンプレックス
劣等感とは、個人が主観的に自分が劣っていると感じ、問題に適切に対処できないと確信していることを指します。
そして、劣等感コンプレックスとは、劣等感を用いて、自らの行動を制限し、成長をためらい挫折を避けようとすることを指します。適度な劣等感は、成長や克服に繋がりますが、大きすぎる劣等感は劣等感コンプレックスとなり、成長や克服を妨げる要因になると考えられています。
- 権力(カ)への意志
人の根本的な原動力を『精神分析』では『リビドー』(性的な欲動)と仮定したのに対し、個人心理学では、権力(カ)への意志であると仮定します。
アドラーは、人には劣等感を克服して自らの弱点を補おうとする心の働きがあると考えます。
このような人間の持つ不完全な状態から少しでも完全な状態に近づこうとする働きが権力(カ)への意志であり、人間の根源的なエネルギーや欲望であると考えました。- 共同体感覚
他者は対立する敵ではなく、互いに結びついている仲間であるという思想を指します。
そして、共通の利益、全体の福祉を尊重し、仲間に貢献できること共同体感覚と呼びます。
参考・引用文献
森岡正芳編 (2022) 『臨床心理学中事典』野島一彦 (監修), 遠見書房.
\この記事を書いた人/
臨床心理士・公認心理師
上岡 晶
Ueoka Sho
精神科・心療内科での勤務を経て、2023年から「オンラインカウンセリングおはぎ」を開業しました。私のカウンセリングを受けてくださる方が少しでも望まれる生活を送れるように、一緒に歩んでいきたいと考えています。