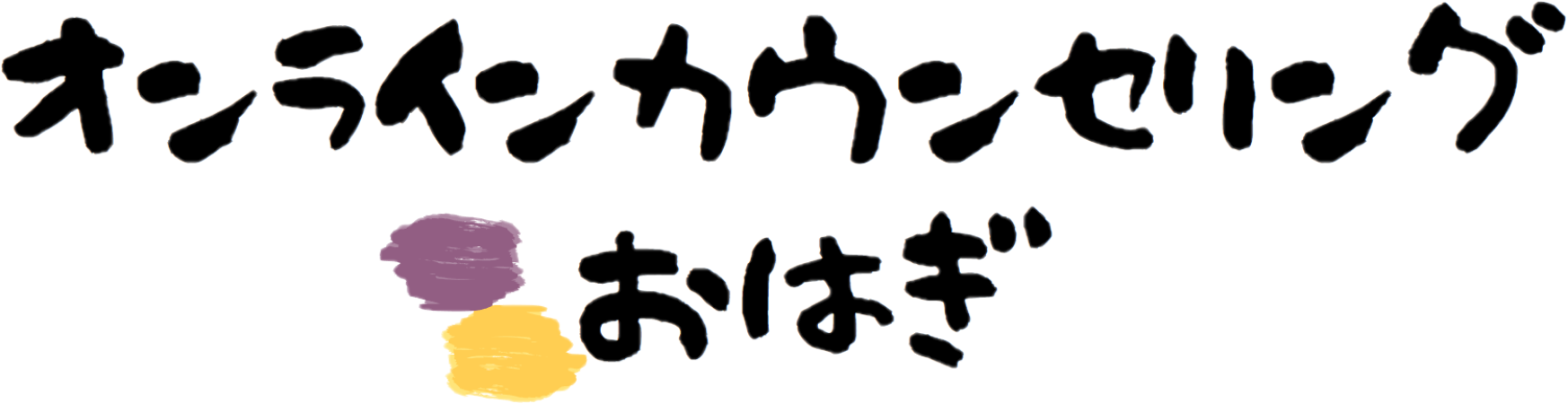メラニー・クライン(Melanie Klein)
メラニー・クライン(Melanie Klein)
“クライン(Klein, M.)”は1882年から1960年に活躍したオーストリア人の精神分析家です。
クラインはオーストリアのウィーンに生まれます。
結婚を機にハンガリーに移り住み、そこで”フロイト(Freud, S.)”が創始した『精神分析』と出会います。
精神分析に関心を持ったクラインは、フロイトの弟子にあたる”フェレンツィ(Ferenczi, S.)”より分析を受けることになります。
そして患者に対して分析を行う精神分析家となります。
その後第二次世界大戦の影響でイギリスのロンドンに移住し活躍します。
クラインは”アンナ・フロイト(Freud, A.)”とともに、子どもへの精神分析の適用を試みた開拓者として知られています。
クラインは、優れた観察眼や洞察力、高い感受性を備えており、子どもの治療を通して様々な概念を生み出していきました。
クラインは、子ども達は外的な世界に生きているのと同時に、同じようにリアリティを持った内的世界に生きていると考えました。
その考えに基づき、『内的対象』や『無意識的空想』『夢生活』など様々な概念を発展させていきます。
そして次第に、クラインの考えは『対象関係論』として整理され、精神障害の治療に大きく貢献していくことになります。
フロイトは神経症の発症について、子どものころに生じる未解決の葛藤が要因となっていると考えました。
そして、その未解決の葛藤は『心理性的発達理論』における、2歳から5歳ごろの『男根期』に生じると考え、その葛藤を『エディプス・コンプレックス』と呼び理解しようとしました。
しかし、クラインは、エディプス・コンプレックスはフロイトが想定しているよりも早期に始まると考え、乳児の心の発達について注目します。
そして、クラインは人の心がどのように発達していくのかについて、『態勢(ポジション)』という考えを用い、『妄想ー分裂態勢(ポジション)』と『抑うつ態勢(ポジション)』の二つを提示しました。
フロイトの心理性的発達理論では、人の心は年齢と共に段階的に発達していくことが想定されています。
それに対して、クラインが提示した態勢では、人の心は段階や時期のようにはっきりとした区別を持って発達していくのではなく、不安や衝動、『防衛機制』などの様々な関連によって変動し、進展していくものだと考えます。
そのため、二つの態勢は、乳幼児の時期だけでなく、その後の成人以降においても使用されると考えます。
クラインは、精神分析理論に基づき子どもの治療を試み、『遊戯療法』を取り入れました。
クラインは、子どもの遊びを大人の治療法に用いられる『自由連想法』と同等と考え、小さな子どもの無意識を解釈することが治療につながると考えました。
その考えは同時期に精神分析の児童への適用を試みたアンナ・フロイトの考えと対立し、論争が巻き起こります。
しかし、その論争は結果的に精神分析の理論の発展や、精神分析家の地位向上に繋がっていくことになりました。
参考・引用文献
森岡正芳編 (2022) 『臨床心理学中事典』野島一彦 (監修), 遠見書房.
日本心理臨床学会編(2011)『心理臨床学事典』 丸善出版.
横川滋章・橋爪龍太郎(2015)『生い立ちと業績から学ぶ精神分析入門 22人のフロイトの後継者たち 』 乾 吉佑 (監修), 創元社.
\この記事を書いた人/
臨床心理士・公認心理師
上岡 晶
Ueoka Sho
精神科・心療内科での勤務を経て、2023年から「オンラインカウンセリングおはぎ」を開業しました。私のカウンセリングを受けてくださる方が少しでも望まれる生活を送れるように、一緒に歩んでいきたいと考えています。