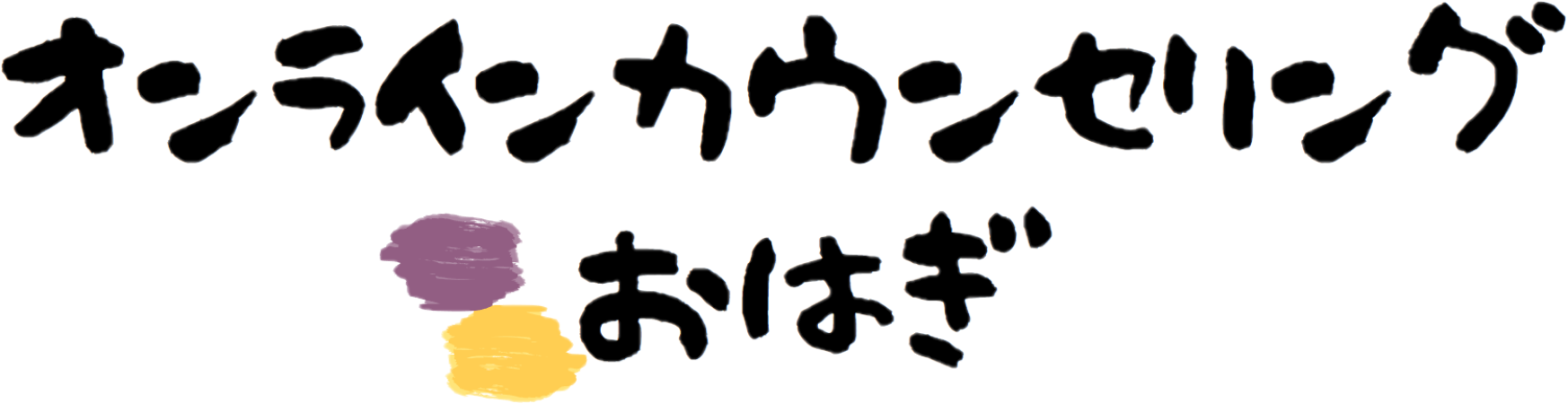メタ認知(meta cognitive)
メタ認知
『メタ認知』は、1970年代にアメリカの“フラベル(Flavell, J. H.)”により用いられようになった概念です。
メタ認知とは、「自分が認知していること」を認知することを指します。
つまり、自分自身の認知過程に関する知識あるいは信念のことを指します。
メタは、ギリシャ語で「高次の」「超越した」という意味を持つ用語になります。
メタ認知は、『メタ認知的知識』と、『メタ認知的活動』の二つに分類されています。
また、メタ認知的活動には、『メタ認知的モニタリング』と『メタ認知的コ ントロール』の二つが想定されています。
- メタ認知的知識
メタ認知的知識とは、自分自身の認知特性(感覚器官から入ってきた情報を理解、整理、記憶する能力の特性のこと)や認知課題に関する知識のことを指します。
例えば、自分は遅刻しがちであることや、パズルを解くのが得意といった自分自身について知っている知識を表します。
もし、自分はパズルが得意なのでパズルの大会に出場しようと 考えたとした場合、メタ認知的知識を利用していることになります。- メタ認知的活動
メタ認知的活動には、メタ認知的モニタリングとメタ認知的コ ントロールの二つが想定されています。
メタ認知的モニタリングとは、認知についての気づきや予想、評価、点検を行う活動を指します。
例えば、数学の問題を解く際に、自分が正しい方法で解いているか確認し(気づき)、答えが合っているか常にチェックすることが挙げられます(点検)。
また、勉強中に理解度を自己評価し(評価)、問題や内容の理解が不十分な場合は再度学習することも重要です。
さらに、テスト準備中に自己テストを行い、知識の確認と理解度の測定を行います(予想)。メタ認知的コ ントロールとは、認知についての目標設定や計画、修正を行う活動を指します。
例えば、数学の試験に向けて毎日2時間勉強する計画を立て(計画)、実際にやってみて時間が足りないと感じた場合、3時間に増やします(修正)。
また、1時間で5問の数学の問題を解く目標を設定し(目標設定)、途中で進捗を確認してペースを調整します(修正)。
参考・引用文献
森岡正芳編 (2022) 『臨床心理学中事典』野島一彦 (監修), 遠見書房.
\動画での解説はこちら/
\この記事を書いた人/
臨床心理士・公認心理師
上岡 晶
Ueoka Sho
精神科・心療内科での勤務を経て、2023年から「オンラインカウンセリングおはぎ」を開業しました。私のカウンセリングを受けてくださる方が少しでも望まれる生活を送れるように、一緒に歩んでいきたいと考えています。