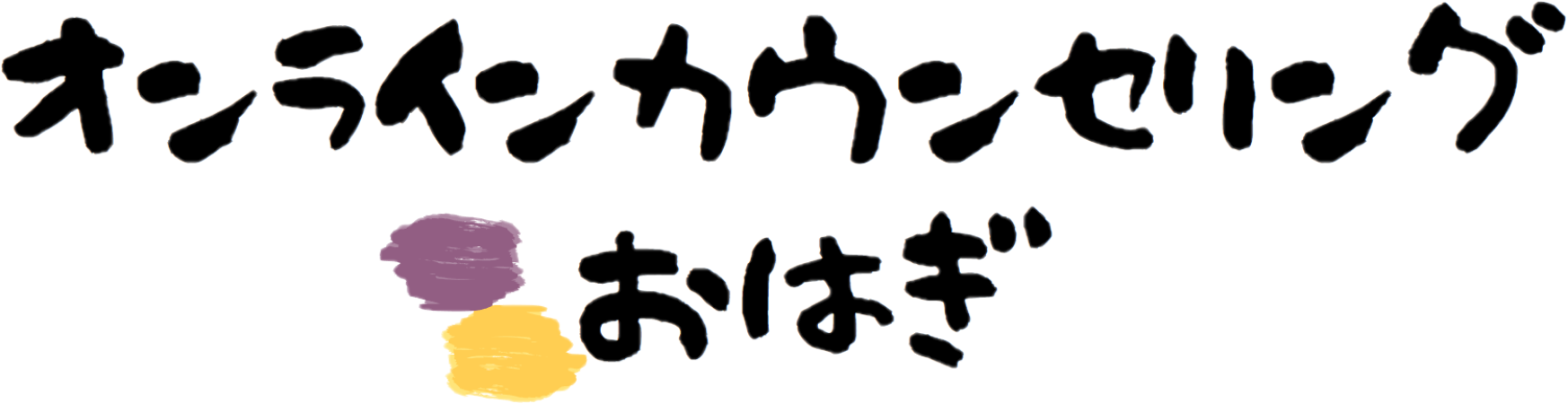対象関係論(object relations theory)
対象関係論
『対象関係論』は、”フロイト(Freud, S.)”が創始した『精神分析』の流れを汲む『心理療法』の1つになります。
“クライン(Klein, M.)”が創始者の一人として知られています。
対象関係論にはクラインの流れを汲む『クライン派』と、クラインとは部分的に異なる理論を展開させていった『独立学派(中間学派)』に分類されています。
クライン派には、クラインの他に、”ビオン(Bion, W. R.)”や”スィーガル(Segal, H.)”、”ローゼンフェルド(Rosenfeld, H. A.)”などがおり、独立学派(中間学派)には、”フェアバーン(Fairbairn, W. R. D,)”、”ウィニコット(Winnicott, D. W.)”、”バリント(Balint, M.)”などがおります。
対象関係論とは、個人の精神内界にある「対象」との関係を軸に人の心を捉え、『精神障害』の理解や治療を行おうとする立場を指します。
心理臨床(人の心や精神障害の理解とその治療)における「対象」という用語は、はじめフロイトにより用いられ始めました。
フロイトは、人の根源的エネルギーを性欲と仮定(『リビドー』論)し、その欲求が葛藤が生み出していく(『欲動理論』)と考えました。
そして、その時に人が性欲や愛着を向ける相手のことを「対象」と呼び理解しようとしました。
ここでの「対象」とは現実に存在している人間というよりも、心の中に存在している他者のイメージを指します。
つまり、幼児期の子どもの場合、リビドーや愛着を向ける相手は養育者(特に母親)になりますが、ここでの「対象」は子どもの心の中にある養育者へのイメージを指します。
そして、対象関係論では、現実での子どもと養育者との関係よりも、子どもの心の中にある養育者へのイメージ(『対象関係』もしくは『内的対象』)を重視します。
このようなことから、対象関係論では精神障害や行動の異常についても対象関係を軸に捉え理解や治療を行おうとします。
つまり、対象関係論では、精神障害や行動の異常は、対象(重要な他者)に対するイメージの歪みにより生じているのではないかと推測します。
そして、そのような対象関係の歪みがどのようにして生じているかを理解し関わることが治療に繋がるのではないかと考えます。
クラインは、このような対象関係を理解し、精神障害の治療を行っていくために、0歳から2、3歳までの非常に早い幼児期の母子関係を研究し、『態勢(ポジション)』などの様々な概念を生み出していきました。
また、多くの研究者や実践家により新たな理論が次々と生み出されていき、対象関係論の発展に繋がっていきました。
対象関係論の発展は、言語によって関係が持てるようになる前の段階の人の心や言語により表現できないほど混乱した人の心の理解に繋がり、また、これまでは治療の対象外とされていた『境界性パーソナリティ障害』や『統合失調症』などの精神障害の理解や治療にも繋がっていきました。
参考・引用文献
森岡正芳編 (2022) 『臨床心理学中事典』野島一彦 (監修), 遠見書房.
日本心理臨床学会編(2011)『心理臨床学事典』 丸善出版.
横川滋章・橋爪龍太郎(2015)『生い立ちと業績から学ぶ精神分析入門 22人のフロイトの後継者たち 』 乾 吉佑 (監修), 創元社.
\この記事を書いた人/
臨床心理士・公認心理師
上岡 晶
Ueoka Sho
精神科・心療内科での勤務を経て、2023年から「オンラインカウンセリングおはぎ」を開業しました。私のカウンセリングを受けてくださる方が少しでも望まれる生活を送れるように、一緒に歩んでいきたいと考えています。