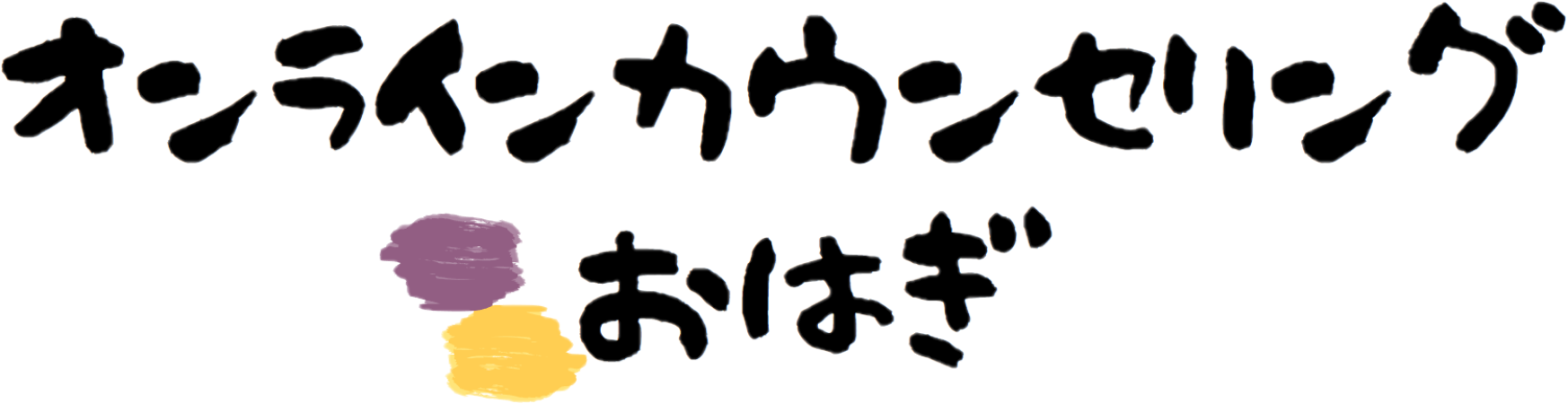心的構造論(structual model)
心的構造論
『心的構造論』は、”フロイト(Freud, S.)”が創始した『精神分析』を構成する理論の一つです。
『神経症』(ストレスなどの影響により、精神が不調となり症状が出る病気)の理解と治療のために生み出された理論になります。
心的構造論とは、人の心を『イド(エス)』、『自我』、『超自我』の3つの種類の機能に分けて理解しようとする理論を指します。
そして心的構造論では、神経症の理解や治療のために3つの機能の役割や相互作用、処理過程に関心を寄せ重視します。
フロイトは神経症を理解する上で、まず人の心がどのようになっているかを理解する必要があると考えました。
そこで、生み出されたのが『心的局所論』です。
心的局所論とは、人の心を『意識』、『前意識』、『無意識』の3つの領域に分けて理解しようとするものです。
つまり、人の心はどのような空間になっているのか、どのような場所があるのかという側面から理解しようとしました。
しかし、心的局所論だけでは、3つの領域がそれぞれどのように作用しあっているのか理解するには不十分でした。
そのため、人の心がどのような動きや働きをしているか理解するために心的構造論が生み出されていきました。
心的構造論では、人の心にはそれぞれ違う役割を持つ機能があると考え、イド(エス)、自我、超自我の3つを想定します。
この3つの機能は『心的装置』とも呼ばれ、人の性格(パーソナリティ)を理解する際にも使用されることになります。
心的構造論では、自我は社会や現実に適応するために、快感原則に従い活動するイド(エス)や道徳原則に従い活動する超自我の働きを調整し、バランスを維持するように機能すると考えられています。
そしてこのような自我の働きは自我の『防衛機制』と呼ばれ、これが上手く機能しない場合に心の安定が損なわれていき、場合によっては神経症の症状に発展し社会や現実での適応が困難になっていくと考えました。
このように、フロイトが想定した心的構造論では、現実適応に向けてイド(エス)や超自我の対立や葛藤の調整を行うといった自我の防衛機能や、治療の『抵抗』を生み出す自我の働きに注目していました。
しかし、1930年代になると”アンナ・フロイト(Freud, A.)”や”ハルトマン(Hartmann, H.)”、”エリク・エリクソン(Erikson, E. H.)”らが現れ、自我はイド(エス)や超自我の対立や葛藤とは無関係に形成される自律した機能をもつ存在であると認識されていくようになります。
そして、そのことが後に『自我心理学』の発展に影響を与えていきます。
このように心的構造論では、イド(エス)、自我、超自我の3つの心的装置がどのように作用しあっているかを理解することで、人格(人の性格)や、神経症、問題行動などについて捉えようとしました。
- イド(エス)(id/Es)
イド(エス)は、人が持つ最も原始的で根源的、本能的な欲求を生み出すところになります。
一部は遺伝的・生物学的に生まれた時から備わっているものですが、もう一部は生まれた後のもので、抑圧された様々な欲動や情動、エネルギーが備わっていると考えられています。イド(エス)は心的(本能)エネルギーの貯蔵庫となっており、このエネルギーは常に満たされることを望み、快感原則に従って活動します。
イド(エス)は心的局所論で言うところの無意識の領域に当たります。
- 自我(ego)
自我は、その後のフロイトの理論の中心となる概念です。
自我は社会や現実に適応するために、イド(エス)や超自我の働きを調整し、バランスを維持するように働きます。
そのため、イド(エス)が快感原則に従い活動するのに対し、自我は現実原則に従って活動します。フロイトは、この自我がうまく機能しないことが、神経症の症状や、問題行動の発生に関わっているのではないかと考え、自我の機能を重視しました。
そして、それはのちにフロイトの後継者達によって、自我心理学の発展へとつながっていくことになります。- 超自我(superego)
超自我は、良心や道徳的、規範的な判断をする機能を持つとされています。
自我の働きを検閲(調べ)し、裁くような働きをします。この超自我は『エディプス・コンプレックス』の克服により育まれます。
「母親への性愛」と「父親への嫉妬」や『去勢不安』を巡る葛藤を同性の親と同一化することで乗り越えようとします。この過程を通して、子どもは親の中にある道徳心や規範性(行動や判断基準)を取り入れることで、人の心に超自我という機能が形成されるようになると考えました。
イド(エス)が快感原則、自我が現実原則に従って活動するのに対し、超自我は道徳原則に従って活動します。
参考・引用文献
森岡正芳編 (2022) 『臨床心理学中事典』野島一彦 (監修), 遠見書房.
\動画での解説はこちら/
\この記事を書いた人/
臨床心理士・公認心理師
上岡 晶
Ueoka Sho
精神科・心療内科での勤務を経て、2023年から「オンラインカウンセリングおはぎ」を開業しました。私のカウンセリングを受けてくださる方が少しでも望まれる生活を送れるように、一緒に歩んでいきたいと考えています。