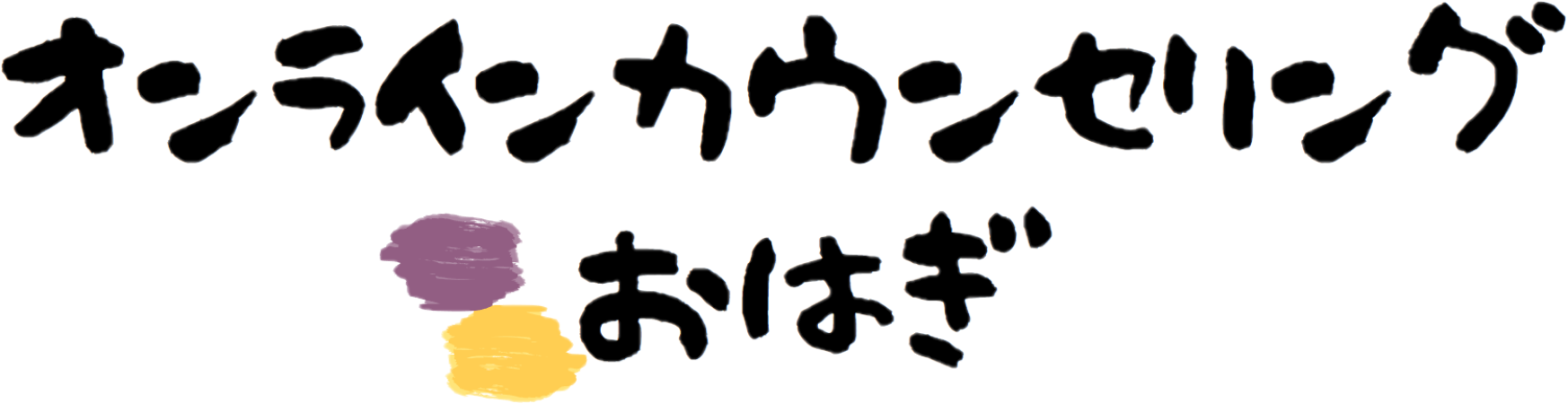心的局所論(topography)
心的局所論
『心的局所論』は、”フロイト(Freud, S.)”が創始した『精神分析』を構成する理論の一つです。
『神経症』(ストレスなどの影響により、精神が不調となり症状が出る病気)の理解と治療のために生み出された理論になります。
心的局所論とは、人の心を『意識』、『前意識』、『無意識』の3つの領域に分けて理解しようとする理論を指します。
そして心的局所論では、神経症の理解や治療のために無意識の内容に関心を寄せ重視します。
フロイトは神経症を理解する上で、まず人の心がどのようになっているかを理解する必要があると考えました。
そこで、生み出されたのが心的局所論です。
心的局所論では、人の心を意識、前意識、無意識の3つの領域に分けて考えて考えます。
フロイトは、無意識の領域には、不快な感情を伴った観念や記憶、また願望が『抑圧』されて存在していると考えます。
そして、無意識の領域に抑圧された観念や記憶、願望が歪曲された状態で顕在化した時に、神経症の症状や『夢』、『失錯行為』として現れると考えました。
このように、心的局所論では意識と無意識の関係から、心や神経症を理解し、治療を試みようとします。
しかし、心的局所論だけでは、3つの領域がそれぞれどのように作用しあっているのか理解するには不十分でした。
そのため、人の心がどのような動きや働きをしているか理解するために『心的構造論』が生み出されていきました。
- 意識
意識とは、自分で自覚出来たり、認識できる心の内容を指します。
また、自分で考えたり、感じていることに気づいていること、自分や周囲の状態がわかっている状態を指します。- 前意識
前意識とは、現時点では、意識の領域にない心の内容を指します。
つまり、普段は意識していないが、思いだそうとおもえば思い出せる領域のことを指します。- 無意識
無意識とは、自分が知らない心の奥深くにある層であり、意識しようと思っても出来ない心の内容を指します。
参考・引用文献
森岡正芳編 (2022) 『臨床心理学中事典』野島一彦 (監修), 遠見書房.
\動画での解説はこちら/
\この記事を書いた人/
臨床心理士・公認心理師
上岡 晶
Ueoka Sho
精神科・心療内科での勤務を経て、2023年から「オンラインカウンセリングおはぎ」を開業しました。私のカウンセリングを受けてくださる方が少しでも望まれる生活を送れるように、一緒に歩んでいきたいと考えています。