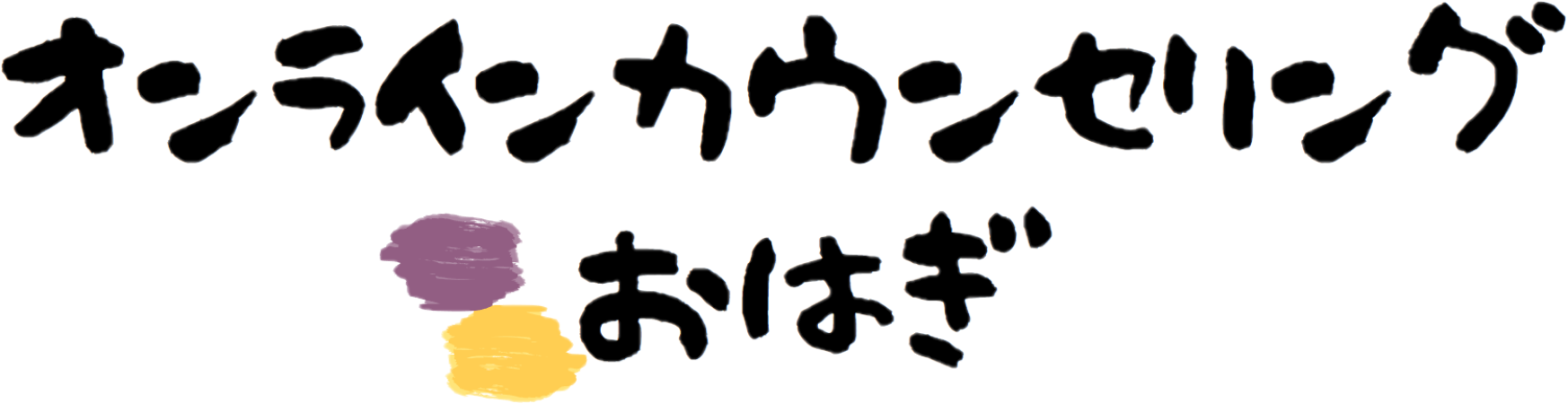自己(self)
自己
『自己』とは、自分自身を意識したり認識したりする存在そのものを指します。
心理学において、自己は『自我』とは異なる概念として説明されています。
自我は、私たちが日常的に感じる私や自分を指します。
具体的には、自分が何を考え、感じ、行動しているかに関わる部分になります。
自我は、私たちの意思や感覚、認識の中心であり、意識の主体にあたります。
一方で、自己は、その自我が意識する自分そのものを指します。
つまり、自己は自我が捉える対象や内容になります。
自己には、自分の全体像や過去の経験、記憶が含まれます。
このように、自我は意識している自分(主体)にあたり、自己はその意識が向けられる対象であり、意識している自分(主体)と意識される自分(対象)の両方を含む概念になります。
たとえば、私はこう考えていると意識する部分が主体である自我であり、その自我が捉える自分全体の姿が自己になります。
自己の構造や成り立ち、発達について、『精神分析』をはじめとする様々な立場から理論が提唱されています。
サリヴァンの想定した自己
『対人関係論』の創始者の一人である”サリヴァン(Sullivan, H. S.)”は、自己とは他者との関係の中で形作られるものであると考えました。
特に自己は、対人関係によって生じる不安を減らそうとする工夫の中で形成されると考えました。
人の不安は、他者からの承認や不承認、賞や罰によって変化します。
例えば、他人から褒められたり認められたりすると不安が軽減し、逆に批判されたり否定されたりすると不安が強くなります。
そのため、人は他者の評価や反応で生じる不安を減らすために様々な方法を試みます。
サリヴァンは、このような過程を通じて自己が発展し、形作られていくと考えました。
このように、サリヴァンは、自己の生成の基底に他者の存在を置き、他者との関係、特に他者からの承認や不承認、賞賛や罰を通して自己は形成されていくと考えました。
ホーナイの想定した自己
また、対人関係論の創始者の一人である”ホーナイ(Horney, K.)”は、すべての人に備わっている各個人の独自の成長と完成を目指す根源的な力を「真の自己」と呼びました。
ホーナイは、『神経症』の発症には、真の自己と「理想化された自己」の間の葛藤が関わっていると考え、治療の目標は患者が真の自己を受け入れ、『自己実現』を目指すことであると考えました。
ホーナイは、神経症の背景に幼少期の『基底不安(基本的不安)』があると指摘します。
基底不安とは、子どもが安全を脅かされていると感じる時に抱く孤独感や無力感を指します。
この不安から自分を守ろうとする中で理想化された自己が作られていくと考えました。
また、子どもはこの基底不安への対処として、「反抗する」「従う」「離れる」といった行動を取りますが、それが過剰になると神経症的な性格が形成されると考えました。
そのため、『心理療法』では、このプロセスを解きほぐし、真の自己を受け入れる手助けをすることが重要だと考えました。
ユングの想定した自己
『分析心理学』の提唱者である”ユング(Jung、C. G.)”は、自己を『意識』と『無意識』の両面を含む心の中心として捉えました。
ユングにとって、自己は単なる自分自身のことを指すのではなく、意識している部分と無意識の中にある感情や記憶、思考なども含めた、もっと広い存在になります。
このようにユングは、心の中の複数の側面が統合されたものが自己であると考えました。
ユングが想定する自己は、意識領域の拡大や無意識との統合に向けて働き、より高い次元へと個人の人格を発達させていく機能を持ちます。
そして、この自己の持つ、その人本来の個性に従って成長していくといった性質や自己実現のプロセスを『個性化過程』と呼び重視しました。
このように、ユングの分析心理学では、自己を人間の心全体と捉え、より高い人格の発達を促す役割を持つものとして重視します。
コフートの想定した自己
『自己心理学』の創始者である”コフート(Kohut, H.)”は、自己を「野心」「理想」、そしてそれらを現実的に調整する「才能と技能」の3つの要素から成るもの(『中核自己』)と考えました。
この3つがバランスよく機能することで、自己は健全に発達し、充実感や安定感を得られるとしました。
コフートによると、自己は『誇大自己』と『理想化された親のイマーゴ』という二つの極から構成されます。
誇大自己とは、幼少期に周囲から承認されることで形成される自己を指し、目標を追求し、自己主張をしていくためのエネルギーや自尊心の源になります。
また、理想化された親のイマーゴとは、幼少期に親や養育者を理想化する体験から生まれる自己を指し、理想を追い求めるための基準や価値観の土台になります。
この二つの極がバランスよく統合され、才能や技能によって現実的に機能することで、自己は一つの全体性を持つ健全な状態になります。
この状態をコフートは『融和した自己』と呼びました。
しかし、幼少期に周囲から適切な関わりを得られないと、自己の発達が停滞し、片方の極に偏ることがあります。
そして、この偏りが強まると、『自己愛性パーソナリティ障害』などの問題に繋がる可能性があるとされています。
自己心理学では、こうした自己の不均衡を治療し、自己の成長を支援することを目指しています。
ロジャーズの想定した自己
『来談者(クライエント)中心療法』を創始した"ロジャーズ(Rogers, C. R.)"は、自己を現象学的に捉えました。
これは、外から見た自分(客観的な自己)ではなく、自分がどのように感じ、体験しているか(主観的な自己)に注目する考え方です。
ロジャーズは、自己とは自分が自分をどう感じているか、どう認識しているかという個人的な体験に基づいていると考えました。
また、ロジャーズの『自己理論』では、自己は自分の経験や他者との関わりを通じて作られる価値観によって形成されると考えました。
自己には、実際の体験に基づく「現実の自己」(『経験』)と、自分が自分自身について抱くイメージや理想像としての「理想の自己」(『自己概念』)があると想定します。
そして、これらが一致しているとき、人は自分を受け入れ、安定を感じることができると考えます。
ロジャーズはこのような自己概念(理想)と経験(現実)が調和している状態を『自己一致』と呼びました。
その一方で、現実の自己と理想の自己がずれてしまっている状態を『自己不一致』の状態とし、その場合、自己の成長は妨げられ人は不安や葛藤を体験すると考えました。
このように、ロジャーズは、理想の自己と現実の自己が調和することで、自己は一貫性を保つことができ、自己実現に向けて成長していけると考えました。
そのため、来談者(クライエント)中心療法では、理想の自己と現実の自己を統合することを目標とし、それによって自分の可能性を最大限に発揮していくこと(自己実現)を目指します。
参考・引用文献
森岡正芳編 (2022) 『臨床心理学中事典』野島一彦 (監修), 遠見書房.
\この記事を書いた人/
臨床心理士・公認心理師
上岡 晶
Ueoka Sho
精神科・心療内科での勤務を経て、2023年から「オンラインカウンセリングおはぎ」を開業しました。私のカウンセリングを受けてくださる方が少しでも望まれる生活を送れるように、一緒に歩んでいきたいと考えています。